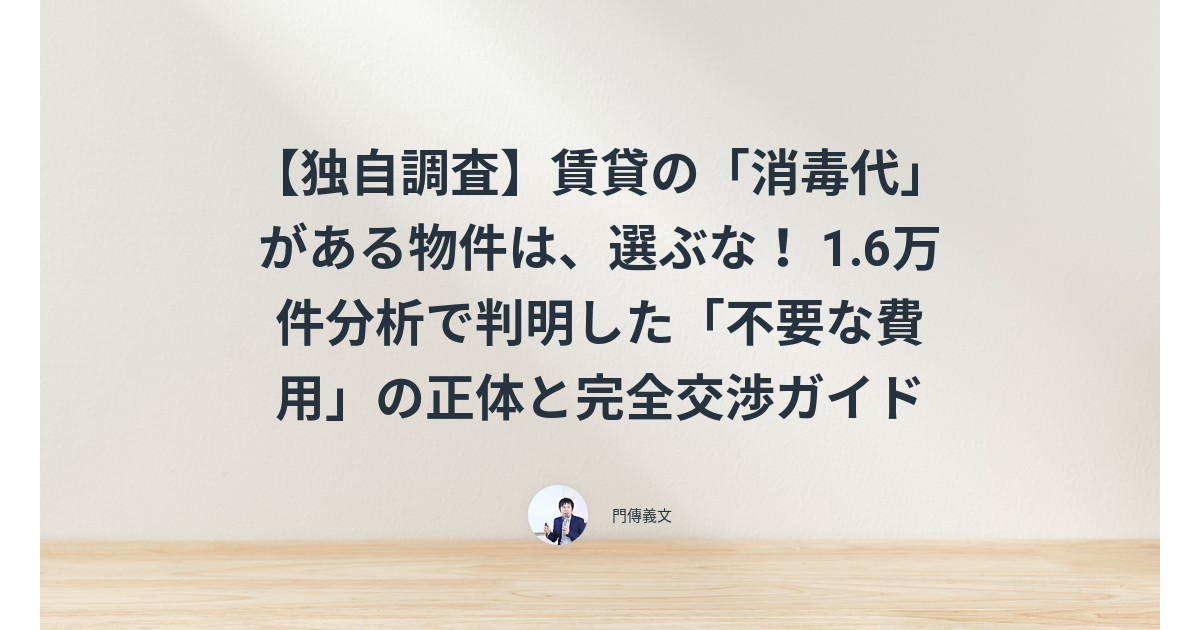賃貸の「消毒代」は拒否できる!1.6万件調査でわかった"不要な費用"の闇と断り方【独自データ公開】
こんにちは、暮らしっく不動産の門傳(もんでん)です。
お部屋探しの初期費用見積もりで、「室内消毒料 16,500円」「抗菌施工代 22,000円」といった項目にモヤモヤしていませんか?
この記事の結論:消毒代は「払う必要なし」
- 法的義務なし:入居者が負担する法的根拠はありません。
- 実は少数派:独自調査の結果、請求している物件は全体の約5.0%のみ。
- 交渉可能:「任意」のオプションであることがほとんどで、拒否できます。
この記事では、15,932件の実際の募集データを分析し、不動産業界の裏側と「角を立てずに断るためのメール例文」を完全公開します。
序章:あの爆発事故と「消毒代」の深い闇
2018年の札幌アパマンショップ爆発事故を覚えているでしょうか。あの事故の原因はスプレー缶の廃棄処理でしたが、その本質的な問題は「実施していない(あるいは簡易的な)消臭・消毒代を入居者から徴収していた」という点にありました。
当時、私はこの問題について業界紙『全国賃貸住宅新聞』から取材を受け、その不透明性を指摘しました。
掲載実績:全国賃貸住宅新聞
付帯商品の問題点が浮上 アパマン問題(2019年01月21日)
※代表・門傳が専門家としてコメントを提供しています。
あれから数年。状況は改善されたのでしょうか? 実態を暴くため、私たちは大規模な独自調査を行いました。
1. 【独自調査】消毒代がある物件はわずか5%の衝撃事実
「消毒代はみんな払っている」「今の時期は必須」という不動産営業マンの言葉は本当でしょうか?
2025年11月時点の募集物件データを徹底分析しました。
調査データの概要
| 調査対象 | 東京主要エリア(新宿・渋谷・中野・世田谷)の募集物件 |
|---|---|
| 分析件数 | 15,932件(2025.11.17現在) |
| 調査方法 | 「消毒」「除菌」「抗菌」「消臭」等の費用項目を全件抽出 |
結果:95%の物件では請求されていない
分析の結果、消毒費用等の記載があった物件はわずか792件。全体に占める割合は約5.0%でした。
※ここに調査結果のグラフが入ります
このデータが証明するのは以下の事実です。
- 「消毒代」は業界の常識ではない(95%は請求していない)。
- 費用が発生しているのは、特定の不動産会社が管理・募集している物件に集中している。
- つまり、物件(大家さん)の都合ではなく、仲介会社の売上アップのための施策である可能性が高い。
さらに、ある物件の資料には決定的な証拠が見つかりました。
「室内消毒代: 15,000円(税抜) 任意」
この「任意」の二文字こそが、この費用の正体が「強制力のないオプション」であることを自白しているのです。
2. 消毒代の正体は「スプレー散布」? 値段のカラクリ
では、1〜2万円も支払って行われる「消毒」とは何なのでしょうか。
ハウスクリーニング(清掃)と混同されがちですが、全くの別物です。
よくある2つのパターン
- 簡易的な害虫駆除(8,000円〜15,000円)
入居前に市販レベルの殺虫スプレーやバルサン的なものを散布する作業。作業時間は10分程度。 - 光触媒・抗菌コーティング(20,000円〜30,000円)
「施工」という言葉を使い、高機能なコーティング剤を壁などに散布するもの。
暮らしっく不動産のホンネ
正直にお伝えします。私たちが管理する物件では、このような別途費用の消毒作業は行っていませんが、「虫が出た」「汚い」といったトラブルは起きていません。
通常のハウスクリーニングさえしっかり行えば、入居者に追加費用を請求するような消毒作業は本来不要なのです。
3. 法的根拠と国交省ガイドラインの見解
「契約条件です」と言われても、諦める必要はありません。法律とガイドラインがあなたの味方です。
国土交通省「原状回復ガイドライン」の原則
ガイドラインでは、次の入居者のために部屋を綺麗にする費用(ハウスクリーニング等)は、原則として「貸主(大家さん)」が負担すべきとされています。
家賃には、すでに「次の入居者を迎えるための準備費用」も含まれているという考え方です。したがって、特別な事情がない限り、入居者が追加で消毒代を負担する合理的理由はありません。
4. 【コピペOK】消毒代を断るための交渉メール例文
ここからは実践編です。電話は「言った・言わない」になるため、必ずメールで証拠を残しながら交渉しましょう。
タイミングは「申し込み後、契約(重要事項説明)の前」がベストです。
パターンA:シンプルに断る(推奨)
お世話になります。初期費用の見積書を確認いたしました。
解説:多くの良心的な会社なら、これだけで「承知しました」と削除されます。
項目にある『室内消毒費 16,500円』についてですが、こちらは不要ですので外していただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
パターンB:健康上の理由で断る(最強)
見積書の『抗菌施工代』について相談です。
解説:最も効果的な断り方です。健康被害のリスクを冒してまで、無理やり施工しようとする会社はまずありません。
私はアレルギー体質(または化学物質に敏感)なため、どのような薬剤が散布されるかわからない作業は、健康への影響を懸念しております。
入居後の体調不良を避けるためにも、室内の薬剤散布・消毒作業は辞退させてください。
パターンC:データと知識で論理的に断る
見積書の消毒費用についてです。
解説:「知識がある客だ」と認識させ、不当な請求を牽制します。
国土交通省のガイドラインを確認しましたが、入居前の消毒・清掃費用は原則として貸主負担であると認識しております。
また、市場調査データを見ても95%の物件では請求されていない費用のようですので、今回は任意のオプションとして外していただけないでしょうか。
5. それでも「必須」と言われたら?最大のリスク回避術
もし、上記の交渉をしても「これは必須条件です」「外せません」と頑なに言われた場合どうするか。
結論:「その物件(不動産会社)はやめる」のが正解です。
「選ぶな」と強く言う理由
たかだか1〜2万円の費用ですが、ここには大きなリスクが潜んでいます。
- 入居中・退去時のトラブル予備軍:
契約時に、法的根拠の乏しい費用を強引に請求してくる会社は、退去時の「敷金精算」でも高額な原状回復費用を請求してくる可能性が極めて高いです。 - 95%の「まともな物件」を探そう:
私たちの調査通り、世の中の95%の物件は消毒代なんて請求しません。リスクのある5%に固執せず、誠実な対応をしてくれる残りの95%からお部屋を探す方が、長い目で見て安心でお得です。
「消毒代」は、その不動産会社が信頼できるかどうかを見極める「リトマス試験紙」です。
不誠実な費用がない、クリアな契約で、気持ちよく新生活をスタートさせましょう。