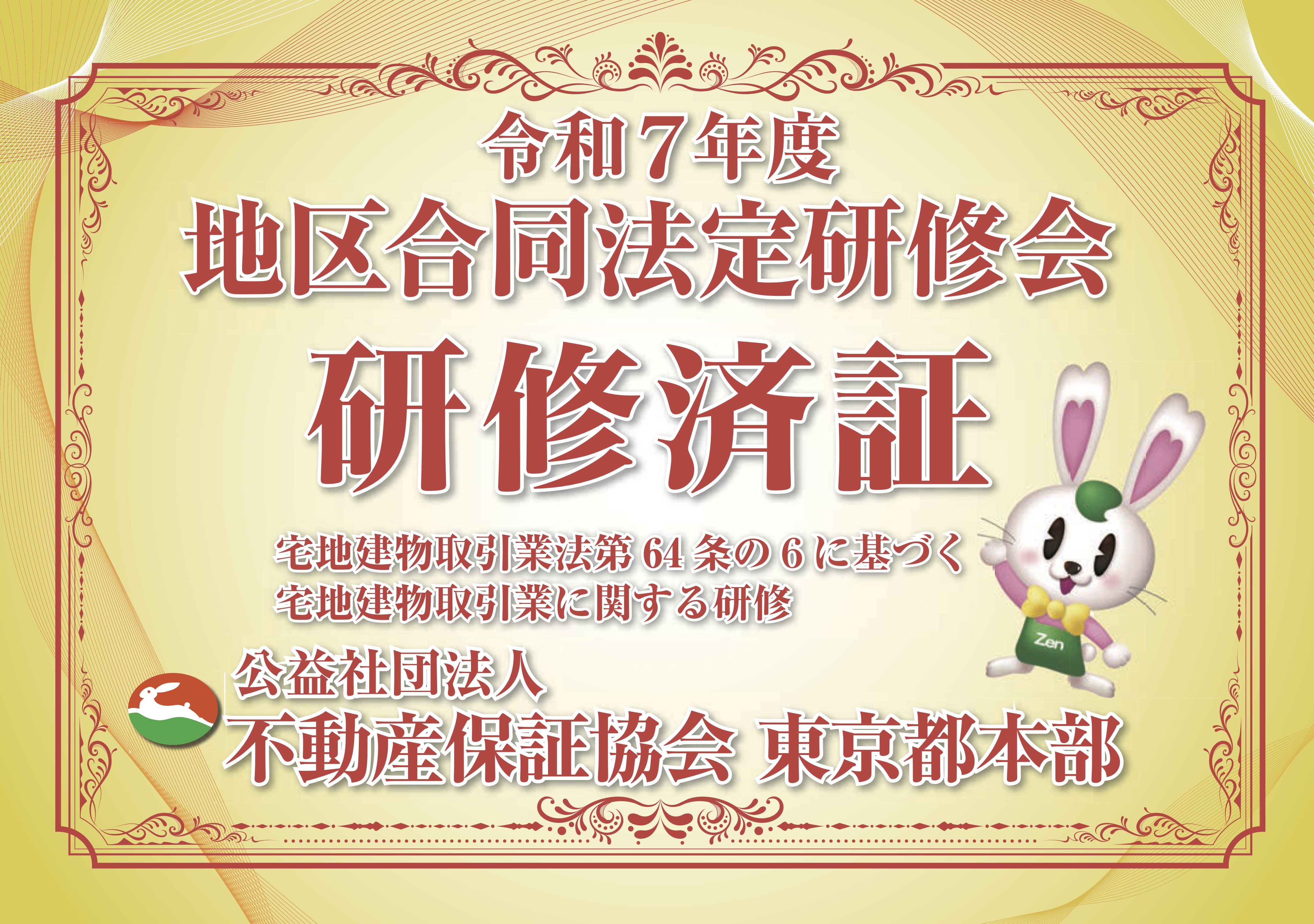「おしゃれな内装」だけで選ぶと失敗する?
不動産のプロが見ている「中古リノベ」3つの落とし穴【2025年法改正版】
こんにちは、暮らしっく不動産の門傳です。
中古物件を買ってリノベーション。「自分好みの空間を作りたい」という相談、よく受けます。雑誌やSNSで見るリノベ事例、素敵ですよね。
でも、正直に言います。
表面的な「デザイン」や「間取り」だけで物件を選んでしまうと、後でとんでもない痛い目を見ることがあります。
「希望の場所にキッチンが動かせない」「隣の部屋の話し声が丸聞こえ」「フルリノベしたのに冬の朝は極寒」……。
これらはすべて、購入前のチェックで回避できる問題です。
今回は、不動産のプロ向けに行われている技術研修資料(※)の内容をベースに、これから中古物件を買う人が絶対に知っておくべき「構造・断熱・法律」の3つの真実を解説します。営業トークには出てこない、リアルな話です。
※参考資料:公益財団法人 不動産流通推進センター「媒介業者が知っておくべきリノベーションの基本知識と最新動向 2024年」他
この記事のポイント
1. マンション購入の落とし穴:「階高」と「GL工法」
内装がボロボロでもリノベーションで綺麗にできます。しかし、「変えられない構造」はどうにもなりません。特に築年数が経ったマンション(築30〜40年以上)で注意すべきは「階高」と「音」です。
■ 天井裏と床下の余裕、「階高」を見ていますか?
「キッチンを壁付けからアイランドにしたい」という要望、多いです。
でも、古いマンションの多くは、コンクリートの床から上の階の床までの高さ(階高)が低く設計されています。これが何を意味するかというと、「床下に配管を通すスペースがない」ということです。
【図解】リノベしやすい構造 vs 注意が必要な構造
階高 2.9m以上
床下に十分な高さがあり、排水管の勾配(傾斜)を確保できる。
→ 水回りの移動が自由!
階高 2.7m未満
配管スペースが取れない。
→ 水回りの移動が不可。
無理に移動すると、部屋の中に大きな「段差」ができる。
■ 音トラブルの元凶「GL工法」
内見に行ったら、壁をコンコンと叩いてみてください。
コンクリートに直接壁紙が貼ってあるのではなく、少し軽い音が響く場合、「GL工法(団子貼り)」の可能性があります。
これはコンクリート壁にボンドの塊(団子)をつけて石膏ボードを貼る昔の工法なのですが、壁とボードの間の空洞が太鼓のように音を増幅させる「太鼓現象」を引き起こします。隣の部屋の音が(特に低音が)よく聞こえる原因になります。
対策:
リノベーションで「GL壁を一度解体して、吸音材を入れた二重壁にする」などの対策が有効ですが、その分解体費用と造作費用がかかります。予算組みの段階で知っておくべきポイントです。
【参考】もっと詳しく知りたい方へ(国土交通省)
2. 「断熱等級4」では寒い!2025年基準の真実
「リノベ済み物件だから暖かいはず」という思い込みは危険です。
2025年4月から、全ての新築住宅に「省エネ基準(断熱等級4)」への適合が義務化されますが、建築のプロの間では「等級4は最低ラインであり、決して快適ではない」というのが常識です。
断熱等級と「冬の朝の室温」比較
※外気温0℃、暖房を消して就寝し、翌朝の室温をシミュレーションした目安
| 断熱等級 | レベル感 | 翌朝の室温 | 体感イメージ |
|---|---|---|---|
| 等級 3 | ひと昔前の家 | 約 8℃ |
極寒。 布団から出るのが辛い。 ヒートショックのリスク大。 |
| 等級 4 | 2025年義務化 | 約 10℃ |
まだ寒い。 暖房なしでは活動できない。 足元が冷える。 |
| 等級 6 | 推奨レベル | 約 15℃ |
快適。 薄手のパジャマで起きられる。 結露もほぼ発生しない。 |
これから長く住むなら、目指すべきは「等級6(HEAT20 G2グレード相当)」です。
中古マンションでこれを達成するコスパ最強の方法は、「内窓(インナーサッシ)」の設置です。壁を壊さずに窓の断熱性を2〜3倍に高められます。
物件選びの際は、「窓枠の奥行き」を見ておくと良いでしょう。内窓を設置するスペースがあるかどうかが分かります。
【参考】もっと詳しく知りたい方へ(国土交通省)
3. 2025年4月「4号特例縮小」で木造フルリノベが変わる
「ボロボロの戸建てを安く買って、柱だけ残してスケルトンリフォームしたい」
そう考えている方は、2025年4月の法改正に要注意です。これまで使えていた「特例」が縮小され、リノベーションのハードルが一気に上がります。
■ 何が変わるの?
これまでは、一般的な木造2階建て住宅(4号建築物)のリノベーションなら、建築士が設計すれば確認申請の手続きの一部(構造審査など)を省略できました。これを「4号特例」と言います。
しかし、2025年4月以降はこの特例が縮小(事実上の廃止)され、大規模な修繕・模様替えには「確認申請」と「構造・省エネ図書の提出」が必須になります。
木造リノベへの影響まとめ
申請費用・審査費用が数十万円単位で追加になる可能性があります。
役所の審査期間が必要になるため、着工までの期間が伸びます。
現行法への適合証明が厳格化されるため、特に「無筋基礎(鉄筋が入っていない古い基礎)」の物件は、高額な基礎補強工事が必要になるリスクが高まります。
対策としては、「確認申請が不要な範囲(屋根の葺き替えや外壁の上張りなど)」で済むような状態の良い物件を選ぶか、法改正に対応できる設計力の高い会社を選ぶことが不可欠です。
【参考】もっと詳しく知りたい方へ(国土交通省)
まとめ:不動産屋にこれを聞こう
リノベーションは魔法ではありません。どんなに腕の良い大工さんでも、建物の基本的な構造や法律の壁を超えることは難しいのです。
これから物件を探す方は、内見の際に担当者に以下の3つを質問してみてください。
- Q1. 「このマンション、階高(スラブ高)は何センチですか? 水回りの移動は勾配が取れますか?」
- Q2. 「この窓に内窓をつけたら、断熱等級はどのくらい上がりますか?」
- Q3. 「(木造の場合)このリノベ内容は、来年の法改正で確認申請が必要になりますか?」
これらの質問に即答できる、あるいは「調べてすぐに回答します」と言える担当者なら、安心して任せられるパートナーと言えるでしょう。
「暮らしっく不動産」では、物件のポテンシャルとリスクを正しく見極めるお手伝いをしています。