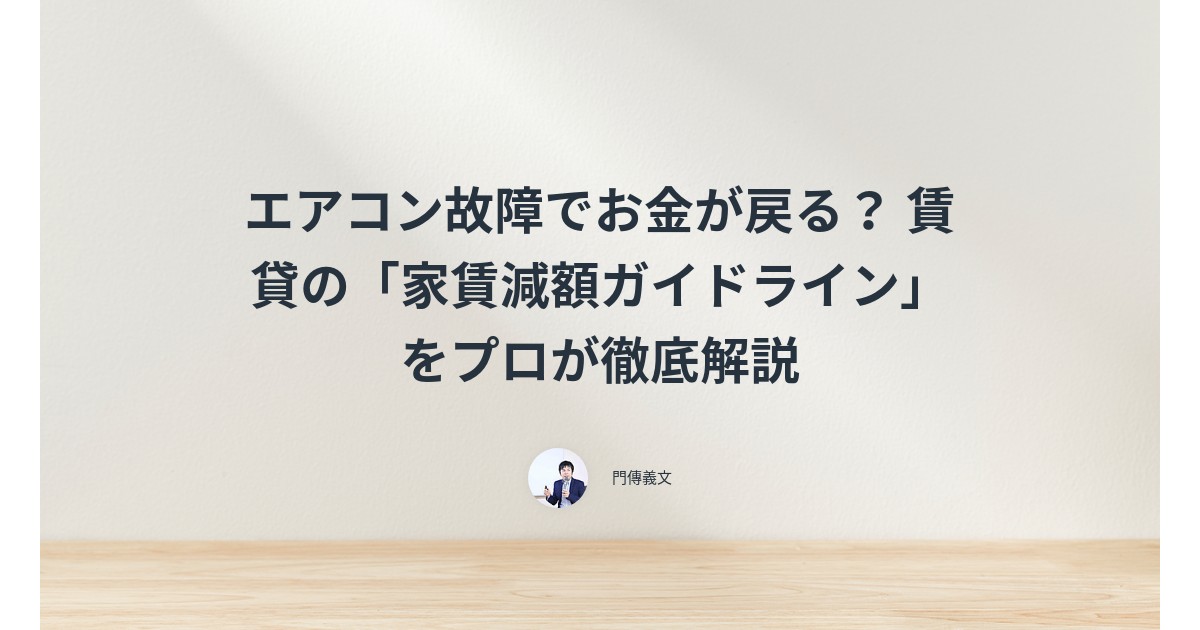エアコン故障でお金が戻る? 賃貸の「家賃減額ガイドライン」をプロが徹底解説
こんにちは、「暮らしっく不動産」の門傳です。
賃貸で暮らしていると、ある日突然、予期せぬトラブルに見舞われることがあります。
「真夏なのにエアコンが壊れた…」
「寒い冬にお風呂のお湯が出ない!」
「トイレの水が流れなくなった…」
どれも想像するだけで焦りますよね。
すぐに管理会社や大家さんに連絡して、「できるだけ早く直してください!」とお願いすると思います。
でも、もし「修理部品がなくて、1週間かかります」なんて言われたらどうでしょう。
家賃は満額払っているのに、まともに生活できない。このモヤモヤ、どこにぶつければいいのか……。
こんな時、借主として知っておくべき「妥当なルール」があります。
それが、「賃料減額ガイドライン」です。
今日はこのガイドラインについて、不動産のプロとして「わかりやすく」徹底解説します。
「業界の普通」ではなく、「一般的な普通」の感覚で、皆さんの疑問にお答えしていきます。
「家賃減額ガイドライン」って、そもそも何?
「設備が壊れたら家賃が安くなる」と聞いても、ピンとこないかもしれません。
大前提として、大家さん(貸主)は、入居者さん(借主)に対して「契約した部屋や設備を、問題なく使える状態」で提供する義務があります。
もし、大家さん側の責任で設備が壊れ、部屋の一部が使えなくなった場合、民法(第611条)のルールに基づき、使えなくなった度合いに応じて家賃は当然に減額されます。
とはいえ、「じゃあ、いくら減額するのが妥当なの?」という基準がないと、大家さんと入居者さんの間で揉めてしまいますよね。
そこで、国土交通省の関連団体である「公益財団法人日本賃貸住宅管理協会」が、トラブル防止の目安として公表しているのが、この「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」 なんです。
実際、どれくらい減額されるの?
このガイドライン、かなり具体的に目安が示されています。
例えば、以下のようなケースです。
- 電気が使えない: 減額割合 40%
- 水が使えない: 減額割合 30%
- トイレが使えない: 減額割合 20%
- 風呂が使えない: 減額割合 10%
- ガスが使えない: 減額割合 10%
- エアコンが作動しない: 減額割合 10%
「電気が使えない」で40%、「水が止まった」で30%というのは、生活への影響度を考えると妥当なラインだと感じます。
【最重要】プロが教える「鵜呑みにしてはいけない」4つの注意点
このガイドラインを見て、「よし、エアコンが壊れたらすぐ10%オフだな!」と思った方、ちょっと待ってください。
このガイドラインは、正しく使わないと逆効果。不動産のプロとして、絶対に知っておいてほしい「重要なポイント」を4つ解説します。これを鵜呑みにしてはいけません。
1. 「免責日数」の存在(壊れた瞬間から減額、ではない!)
これが一番の勘違いポイントです。
ガイドラインには「免責日数」という考え方があります。
これは、「修理や部品の手配に、常識的にかかるであろう日数」のこと。
例えば、エアコンや給湯器の免責日数は「3日」、トイレは緊急性が高いので「1日」 と設定されています。
この「免責日数」を超えた分から、初めて減額の対象となるのが一般的です。
(条件:月額家賃10万円、免責日数3日、減額割合10%)
1. 減額対象となる日数:
6日間 - 免責3日間 = 3日間
2. 1日あたりの減額金額:
(家賃100,000円 × 減額割合10%) ÷ 30日 = 約333円/日
3. 減額合計額:
333円 × 3日間 = 約1,000円
「壊れた!すぐ減額!」ではない、という点は冷静に理解しておきましょう。
2. 法的な拘束力はない「目安」である
このガイドラインは、あくまで「目安」であり、法律のような強制力(法的拘束力)はありません。
「この通りにしろ!」と強く主張するためのものではなく、大家さんと入居者さんが円満に解決するための「妥当な基準」として参考にされるものです。
交渉の「武器」ではなく、「話し合いのテーブルに乗せる資料」と考えましょう。
3. 「自分のせい」は当然ダメ(借主の過失)
当たり前のことですが、借主の過失(不注意やわざと)で設備を壊した場合は、減額の対象外です。
- 「エアコンを自分で掃除したら、部品を壊して動かなくなった」
- 「お風呂の排水口に異物を流して詰まらせた」
このような場合は「善管注意義務違反」となり、減額どころか、修理費用を請求されることになります。
4. 対象は「貸主設置の設備」だけ(持ち込みエアコンは?)
これも非常に重要なポイントです。
減額の対象となるのは、あくまで「貸主(大家さん)が設置した設備」の不具合です。
よくあるのが、入居者さんが「自分で購入して設置したエアコン」のトラブル。
これが水漏れを起こして壁紙にカビが生えた…といった場合、これはガイドラインの対象外です。
むしろ、壁を汚したこと(善管注意義務違反)で、大家さんに対して損害賠償義務(修理費の負担)を負う可能性すらあります。ご注意ください。
実際にトラブルが起きたら、どう動くべき?
では、実際にトラブルに見舞われた時の「正しい行動」をステップで解説します。
STEP 1 落ち着いて記録する
まずは冷静に状況を把握します。
- 「いつから」(例:〇月〇日の夜〇時頃から)
- 「何が」(例:キッチンの給湯器)
- 「どうなったか」(例:エラーコード「111」が出てお湯が全く出ない)
可能であれば、エラーコードや水漏れ箇所などをスマホで写真や動画に撮っておきましょう。これが後で「証拠」になります。
STEP 2 速やかに管理会社(または大家さん)へ連絡
記録したら、すぐに管理会社や大家さんに連絡します。
「いつから」「何が」「どうなったか」を正確に伝え、修理を依頼してください。
この時、「連絡した日時」も必ず控えておきましょう。
STEP 3 修理が長引く場合は「相談」する
免責日数(エアコンなら3日)を過ぎても、修理の目処が立たない、連絡がない…。
そんな時は、ケンカ腰ではなく「相談」という形で、このガイドラインの存在を提示してみましょう。
「〇〇の件、まだ直らないようですが、生活に支障が出て困っています。日本賃貸住宅管理協会のガイドラインなども参考に、修理完了までの賃料についてご相談できませんでしょうか?」
このように、冷静に、誠実な交渉を求めることが大切です。
まとめ
「不動産業界の普通」ではなく、「一般的な普通」の感覚として、家賃を払っている以上、安心して住める環境が提供されるのは当然のことです。
この「賃料減額ガイドライン」は、万が一の時にあなたを守ってくれる「お守り」のような知識です。
借主・貸主双方が正しい知識を持ち、誠実に対応することで、不要なトラブルは必ず避けられます。
暮らしっく不動産では、これからも皆さんの賃貸生活に役立つ「リアルな情報」を発信していきます。