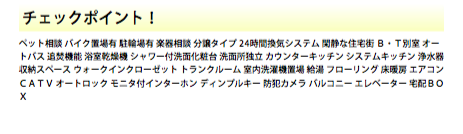「オポサイト」
トタンに雨が打ち付けるみたいに、私が歩くたびに階段が鳴る。自分の存在が響き出すようで嫌いじゃなかった。
あまりの残暑に耐えきれずに、コンビニに避難し、特に買うものもないのにうろうろして、カロリー0のサイダーだけ買った。蓋を開けると、大げさにプシュッと音がして、蓋を持つ親指の付け根にサイダーの粒が噴き出したのが分かった。
コーポの玄関を開けると、付けっぱなしにしていたテレビが笑い声で迎えてくれ、開け放したベランダの網戸のむこうには、立派なマンションが見える。
なんで引っ越したの、と聞かれて用意している答えは、実家からも近いしコンビニもあるし友達も呼べないことないし、家賃安いから苦しくならないし、結婚とかも予定ないから自由にしようかなと思って。というものだった。
暦に反して、マンションの上をいった太陽の陽がカーテンの裾から伸びてきて気持ちがいい。コーポだけど花も植えてくれているし汚くはない。それに、都内ならいつだって大好きな夢の国みたいなテーマパークにも行ける。ベランダにはプランターでトマトも育てられるし、床も入居のときに淡い色の木目にしてくれていて落ち着く。ね、だからここにしたの。

午前10時45分、いつもとほぼ変わらない時間で、向いのマンションのバルコニーで洗濯物を干す満里奈の姿を捉える。女と一緒に住む佑司が仕事に向かったのだと分かった。カレンダーの休日に関係なく、仕事に出掛けるシステムエンジニアという仕事はやっぱり大変そうだなぁと思う。
私は網戸越しに目を細める。眩しい。満里奈がパタパタと洗濯物のしわを叩く音がこっちまでぼんやり届き、物干竿にハンガーをひっかけているのが見える。シーツだろうか、バルコニーの手すりに大きめの布を広げている。見上げる格好が首にくるので、空気のいっぱい入った旅行用の首まくらを巻いた。そうしている間に、バルコニーでぺらぺらと薄いグリーンの水玉のシーツの角が揺れた。
あーーーー!! と叫びたくなるのを我慢する。今日も私がここにいると知らずに、満里奈は洗濯物を干し終わったようだった。
もうすぐ11時になる、満里奈が仕事に向かう時間だ。満里奈もシステムエンジニアをしているが、正社員ではないので少し遅い。そして佑司よりも帰宅が3時間ほど早い。佑司の年収は500万もいかないくらいなはずで、満里奈が仕事を辞めても余裕というわけにはいかないんだろう、と知っていた。二人の新居はステキなマンションがいいけれど高い階の部屋に住むのは難しいだろう、ということも知っていた。
私は、玄関を出、コーポを出て、ぐるっと左周りに歩いてマンションのエントランスに向かった。綺麗に整備されているから、遊歩道になっていたりベンチが置いてあるのが私には好都合だった。

私は、息を止めて、さも散歩の途中の休憩ですよと言わんばかりにベンチに腰掛け、横目でマンションのエントランスを見ていた。
すっと満里奈が通っていった。長い髪をポニーテールにして、ボーダーのTシャツの上に紺のジャケットを羽織っていた。誰も見ていないと思っているからか気の抜けた横顔だった。笑わなくても見えてしまう出っ歯がやっぱり嫌いだと思った。パンツはピンストライプに見えて、ボーダーとストライプを合わせるあたり、ダサいなと思った。満里奈があの家から出ていったことに、ちょっと気持ちが落ち着いた。
初めて佑司に出会ったのは、大学2年生の頃だった。テーマパーク内のレストランでアルバイトをはじめたときに、私よりも少し前から働いていたのが同い年の佑司だった。私はホールで、テーブルを拭いたり注文をとったりし、佑司はキッチンでキャラクターの形のデザートを作っていた。耳の切れてしまったデザートをまかないでもらったときは、オレンジのゼリーが口の中でちゅるちゅると転がったのを覚えている。

1年ほどした日、会計トラブルがあって帰りが遅くなってしまった夜、佑司が家まで送ってくれると言った。家がそんなに離れていないことを知っていたから、じゃあ一緒に帰ろう、と私は返事をした。佑司は実家のママチャリで来ていて、私はひざ下のスカートが車輪に巻き込まれないように横座りで後ろに乗った。
高校生じゃないんだから、と笑いながら、私は揺れる体で佑司の腰を抱きしめた。まだ夏前なのに佑司の背中は暑かった。佑司が何かしゃべるたびに、風に声が飛んでしまいそうだったけれど、耳を背中につけていると、声がくぐもって響いてきた。
私の家のそばで、じゃあまた、と言いながら降りると、佑司は、付き合えないかな、と言った。私は、たぶん何秒かぼんやりしてしまって、佑司は今どうこう言わなくていいから、帰ったらメールする、と、さっと自転車をこいで行ってしまった。
初めてできた彼氏なんだよ、とその数日後にカフェで佑司に話したら、まじでっ、とびっくりしながら、喜んでくれた。絶対幸せにするから、なんて子供みたいな大人みたいなことを真面目な顔をして言ってくれた。
社会人になって2年目で、私と佑司は別れた。その時は、決定的な何かがあったわけではなかった気がしていた。休日が合わなくてなかなか会えなかったことが多かったし、仕事の相談をお互いにできなかったのかもしれないし、私が慣れてしまってわがままだったのかもしれない、と思った。別れてすぐ、バイトの時に後輩だった満里奈と付き合い始めたことを知った。SNSを外さないでいたから、交際中です、という表示がある日急にくっきり浮かんできた。
おかしいだろ、と思った。別れてたった数日の話だった。満里奈と付き合うために私と別れたかったんだ、とその時に知った。佑司はSNSの更新が滞っているのか、見せる相手を限定にしたのか分からなかったが、見ることができなくなっていた。だから、満里奈のSNSを初めて見てみると若い女の子らしくことあるごとに何か書いていた。行列で食べたパンケーキ、風で飛んできたビニール袋、新しいタブレット、手料理のハンバーグ、そのどの写真にもいちいち佑司の存在をちらつかせていた。別れる3ヶ月も前からだった。

私は佑司に連絡をした。今までありがとう、一緒にいられて幸せだったよ、わがままだったかなごめんね、もう新しい彼女がいるのかもしれないけど、楽しく過ごせるといいね、とメールをした。
その日の夜に佑司から返事が来た。そんなにすぐ他の彼女ができるわけはないけど、俺も楽しかったよありがとう、そっちも幸せになってね。また友達として飲みに行こう! と書かれていた。
私は、あっさり、彼女でもなんでもなく、そっち、になっていた。それから佑司と満里奈の交際はずっと続いていた。ほとんど連絡を取らなくなって、4年がたっても、他の男の人と付き合っても、どこかで佑司と比べていた。比べて、佑司が一番好きだったと思う。好きだったじゃない、好きだと思った。
私はSNSを止めたし、佑司と満里奈に見ているとも思われたくなくて、なるべく見ないようにしていた。数ヶ月たって、1年がたって、やっぱり佑司はどうしてるかなと思った時、一緒に飲んでいた女友達にスマホを借りて、女友達のSNSに入れてもらって、トップ画面から佑司の名前を検索させてもらった。
画面に、"満里奈さんは佑司さんと既婚です"と表示された。検索した日のちょうど2ヶ月前の日に"結婚"と表示されていた。
私が次の誕生日に食べたいと言っていたフルーツいっぱいのホールケーキを満里奈が食べ、私が一緒に行きたいと言って行けないでいた大分の温泉に満里奈が行き、ドライブするならあんな車がかわいいよねと私が言った車の助手席に満里奈が乗り、実家も海も見渡せるところで結婚式をしてみたいと私が話したチャペルで満里奈がウエディングドレスを着ていた。
写真のなかの誰もがこぼれんばかりの笑顔で、佑司は満里奈が差し出したケーキのクリームを口中につけていた。コメントには私の知らない人たちが末永く幸せになってね、と書きつづっていた。
それから、満里奈の住居が都内になった。佑司と満里奈の現在の職場から近いということや、満里奈が休日に立ち寄るカフェや、喜びに満ちあふれた新居の写真から、どこのマンションに2人が住みはじめたのか、だいたい分かった。
平日の昼間に、買い物帰りの住人を装ってマンションを見に行くと、オートロックのガラスドアが大きかったおかげで、並んだ郵便ポストの名字が見えた。203号室だった。
私が引っ越してから半年がたとうとしているが、私は向いの家が佑司と満里奈の住まいであることに何の後悔もしていない。愛情はいつのまにか愛憎になっているのかもしれない。傷つけたいだなんて考えたこともない。でも、2人がこのまま幸せでいられますように、なんて思ってはいない。
コーポに戻ると、付けっぱなしのテレビから昼間特有の賑やかさが漏れて来る。1週間のワイドショーのまとめをしている。タレントと不倫したミュージシャンに新恋人か、アイドルグループ解散までの真実、などと進行のアナウンサーが声を張った。タレント相手のときはいいじゃんと思ったのにミュージシャンの次の相手が一般人というのが気に食わない、解散の原因となったメンバーのほうが正しいんじゃないか、とぼんやり思い、自分はどこか世間とズレているのかと不安になった。
向いのマンションのHPを開き、メンテナンス管理会社を探す。出て来たメンテナンス会社に電話をかけた。丁寧な挨拶のあとで、何かお困りの事がございましたでしょうか、と電話の向こうで女性が言った。さすが高いマンションは違う、と思いながら、外出先のために電話番号が違っていたら申し訳ないのですが、と前置きして、お風呂場の換気扇の調子が悪いようなんです、と答えた。売り出された際のマンションの設備に関してはPDFでいくらでも見ることができた。
どのような症状でしょうか、と聞く女性に、浴室乾燥の風がうまく出ないのと換気扇の中でガラガラと何か部品が飛び散るような音がすごくて、と答えた。修理をしてもらえるなら3日後に来てもらえるとありがたい、と伝えると、では3日後にメンテナンス業者を向かわせますので部屋番号と念のためお名前とご連絡先をお願いします、と女性が言った。私は、203号の、契約者は田井佑司で、と答え、佑司の携帯電話番号を伝えた。女性は、かしこまりました、では修理の者が参りますのでよろしくお願いいたします、と言った。私は、ふぅっと小さく息を吐いて、床に大の字になった。開けっ放しのベランダから入り込むちょっと湿った空気が気持ちよかった。
勢い良く立ち上がり、スーパーへ出かけて、数日分の食材を買った。二人のいないマンションの向いの部屋でやることなんてなかった。その日に安くなっている野菜で、お弁当に入れられるような常備菜をいくつも作った。休日はこれで日中を過ごす事が多いが、料理をしていると気持ちが落ち着いていくのが分かった。
ささみとブロッコリーの炒め物、高野豆腐とにんじんの煮物、切り干し大根とえのきのみりん醤油、マカロニサラダ、ほうれん草のおひたし、なすの煮浸し、ごはんも3合を炊いた。
昼下がりのバラエティ番組がいつのまにか夕方の情報番組に変わっていて、私はテレビを消した。そろそろ満里奈が帰ってくる頃だった。向いのマンションにパッと明かりが灯った。バルコニーから見える満里奈は、電話をしているようだった。
しばらくすると満里奈が電話を終え、バルコニーに出て来た。つまづくようにサンダルに足を突っ込んだようで、ゆっくりと洗濯物を取り込んでいる。ちらっと見えるポロシャツが、佑司の好きなショップのものに見える。
満里奈も佑司も、寝る直前までレースのカーテンしか閉めない。私にとっては幸運な話しだが、きっと二人にとっても、バルコニーから見えるこのコーポの上空の夜の星や月、整備された遊歩道を目に入れるのが満足なんだろうと分かる。
夜8時過ぎに、佑司が帰ってきた。部屋の中で2人が何を話しているのか、どんなふうに夕食をとっているのか気になりながら、同じ時間に、私は今年はじめての冷やし中華を食べた。
夜9時頃、バルコニーが勢い良く開いた。私は、そっとベランダの近くにしゃがんで2人を見た。佑司と満里奈のバルコニーには、外でお酒を飲めるようにアウトドア用のイスが並べられているのを覗き込んで知っていた。そしてそのイスは、私と佑司が夏フェスに行ったときに買ったものと遠目から見てもよく似ていた。
2人はイスでビールを飲んでいる。今日一日のことでも話しているのだろう、お互いに顔を合わせてばかりだ。佑司は、私と付き合っていた頃は、私が友達との予定を入れると、その日会えたのになんで友達のほうと予定決めちゃうの、などと何度も言っていた。私と結婚してもこんなふうに、昼間別々でも穏やかに会話ができたのかと思う。
満里奈が何か言って、佑司が手を叩いて笑った。ビールもう一本、というそぶりで機嫌良く立ち上がった佑司に、満里奈が見上げて何か言った。佑司は手にしていたビールの最後の一滴を飲み干す様に頭を反らせた。その雰囲気から、佑司が飲み物を買いに出掛けようとしているのが分かった。
私は急いで、財布を持って、洗面所で髪を整え、メイクの落ちかけた顔にパウダーだけはたいた。玄関を開ける音、鍵を閉める音、私が階段を降りる音だけが日が暮れたコーポに響いた。
コーポの入り口で、一度だけ見たことがあるようなおばさんを見つけた。コーポの管理だか持ち主だかの、中山さんだか葉山さんだった気がする。でも挨拶をしている時間はない。
走ってマンションのそばまで行き、昼間に満里奈を見送ったエントランスの入り口に立った。エレベーターから出て来る佑司がはっきりと見えた。バルコニーで白いTシャツに見えた服は、薄いボーダーの柄が入っていた。
スマホを見ながら歩いてきた佑司がマンションの自動ドアを通る。私は、マンションの住人であるかのように入れ違いに自動ドアを通り、わざとぶつかった。
佑司が、わ、すみません、と言いながら、私を見た。佑司は、ただ、なんだかわからないような表情で、私を見つめた。
佑司も私もその場から動かず、立ち尽くすようにお互いを見つめた。
自動ドアが律儀にドアを開け続けてくれていた。