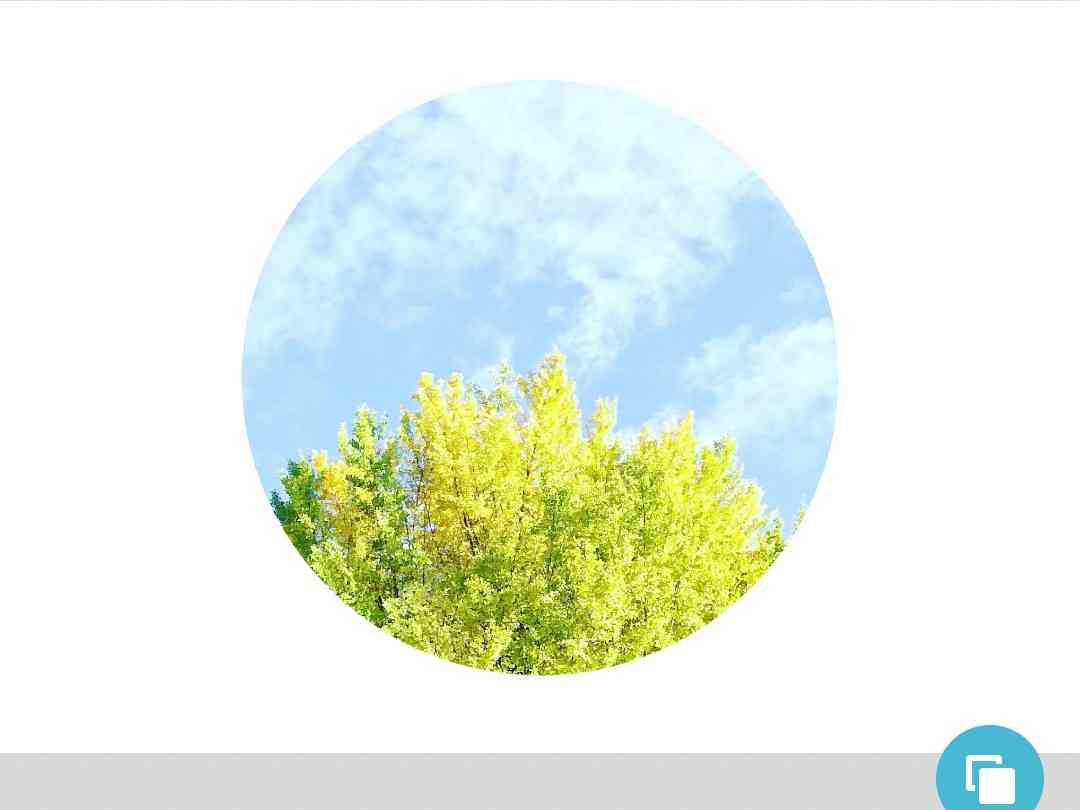「ぼっちとは、学校、主に大学で友達がおらずいつもひとりぼっちであること。恋人がいないときにも用いる。ひとりでの食事はぼっちメシなどと言われる。学生の場合には、昼休みや教室の移動を苦手とする人が多い。必ずしもぼっち同士が仲良くなれる、というわけではない」
まなぽんがスマホを読み上げ、うわ、つらぁ、と言って私を見た。
「やだよ憐れまないでー」
「大丈夫だよ、ゆみかには私がいるじゃん、ぼっちじゃないじゃん」
「でも大学ではぼっちなんだよう」
「それはつらい」
「でしょ」
「サークルは?」
「そもそもの原因がサークルなんだもん」
「マイコって子だっけ?」
まなぽんがキャラメルラテをふぅふぅとしながら私を見るので、私はソイラテをカップの中でぐるぐるさせながら頷いた。
「ゆみかのせいじゃないじゃん、マジ迷惑なんですけどマイコって子」
「そうだけど...」
「だいたいさー、その、誰だっけ、ケータ先輩?が、ゆみかのこと好きになったって言ったら急に無視とかありえないよね」
「うん。女子ってそういうものなのかな。まなぽんは彼氏いるから分かる?」
「いや、だいたい彼氏がほかの子好きだからとかなくない? ケータって人とマイコが付き合ってたんなら話も変わるけど、だいたいマイコが一方的に好きだったってことでしょ」
「うん」
「でもケータって人もさぁ、わかるじゃん?そんなマイコみたいな女の子いたらめんどくさいことになるって。それを知っててゆみかに手だすとかさ」
「手だされてないよ。デート誘われてキスされただけ」
「それを出されてるって言うんだよー!」
「それでケータがそれマイコに言って、マイコが泣いて、サークルにゆみか無視ねってなってるんでしょ?」
「うん。こんなことある~? もう最悪」
「ケータはどうしたの?」
「いいなって思ってたけど、すっごい気まずくなって、こんなんで付き合えないし、慶太先輩サークル内で相談とかしちゃってて、サークルも行きづらいし、サークルの子とかで授業も一緒だったから、教室とかでもぼっち」
「マジぼっちじゃん」
「うん。ねぇ、どうしよう。どうしたらいいと思う?」
「えー、大学以外では私もいるしさ、ぼっちじゃないから、とりあえず大学は勉強しに行くみたいに割り切れば?」
「それしかないかなぁ? でも後期入って毎日だよ?つらいよー。もう帰ろうかな田舎」
「ちょっと待て!それはダメっしょ。お母さんびっくりしちゃうっしょ」
「うーん、まなぽん、ぼっちの寂しさどんなか分からないでしょ?」
「分からないことないって。あれでしょ?高校のときの伊藤みたいな子ってことでしょ?」
「そうだけど。いま思えば伊藤さんよくひとりで昼休みとかいられたよね。私もうなんか、ぼっちっていうことより、あぁこの子ぼっちなんだ、みたいに思われるのもつらい!」
「うー、かわいそう」
「とりあえずぼっちになったから大学辞めたいとかヤバいよね?」
「やばいけど...ぼっち大変...」
「さっきからぼっちぼっち言い過ぎだよね? マジつらい」
「ごめんごめん、だってぼっちなんだもん」
「そうなんだけどさぁ」
「あ、わかった! じゃあ大学の中で新しいことはじめてみるとか? 新しいサークル入るとか」
「いまから入れるところなんてあるのかなぁ。もう秋すぎるよ?」
「夏のはじめにぼっちになったんだから夏がおわったんだし、ぼっちも終わりにすればいいじゃん!後期失敗したって年末一緒に田舎帰れるし」
「んー。たとえば?」
「たとえば、テニサーみたいのじゃなくて、地味なサークルにするとか!」
「漫画研究会とか?アニメサークルとか?」
「それは好きじゃないと無理くない?」
「うん。じゃあ...映画研究会とか歌舞伎サークルとか、落語とか、写真とか、旅行サークルとか」
「あ、写真、超いいね!かっこいいね!」
「写真かぁ、結構好きだけどほとんどカメラも持ったことないのに?」
「とりあえず行ってみたらいいんじゃない?」
まなぽんが言いながらラテに口をつけると、上唇にふわっとしたラテの泡がついて小動物みたいだ。

そっか、そうかも、と返事をしてみると、なんだかちょっと新しいところを覗いてみるのも良いのかもしれない、という気持ちになってきて、スマホで大学の写真サークルの情報を探した。
「あ、あったかも」
Twitterには綺麗な写真があげられていて、大学公認サークルphoto mook(フォトムック)と書かれていた。
「綺麗、ここゆみかの大学?」
「たぶん、だけどこんな綺麗な校舎あったかなぁ?」
画面には、重厚感のある石で造られたような白い壁に、はめこみのように小さなガラス窓が均等に並んでいた。ガラスから陽がさしていて、ガラスからのびる光がピアノの鍵盤のようだった。

「こんなの撮れたらすごくない?」
そう言うまなぽんに、私も、うん、と返すと、バッと、自分が一眼レフのカメラをくびからさげて大学のキャンパスにレンズを向けている姿が浮かんだ。
「ゆみかどしたの?」
「うん、なんか、ほんとにいいかもしれない、写真のサークル」
「でしょ!ゆみかに合いそうだもん。マイコみたいな子がいたらやめといたほうがいいかもだけど、一回見学でもさせてもらえば? 来年になったら新入生ばっかりの勧誘になっちゃうから今のうちじゃない?」
「たしかに。なんか普通に新入生のときにもっと見ておいたらよかったな。なんか人気ありそうだしみんな入るっていうし、っていうのでテニサーにしちゃったんだよね」
「でもできたばっかの友達がみんなやるってなるとそうなるよね、わかる。でもいまからでも遅くないって」
私は、うーん、と言いながらサークルのtwitterにメッセージを送った。
途中からサークルなんて入りづらいなと思うけど、このままぼっちで何もできないのも困るという気持ちも強かった。
「ゆみかが写真撮れるようになったら撮ってもらおうかな~盛れてるやつ」
「まだやるかも決めてないのに、気が早い~」
「あ、ちょっと元気でてきたね、よかった」
そうだね、とまなぽんに返事をしながら、イメージとちがうなぁと改めて思った。ほんとなら今頃、彼氏ができて原宿とか表参道とかでデートしてたはずなのに。
彼氏がいないのは百歩譲ってよくても、友達とハロウィンでウォーリーかマリオになる予定も遠くから聞いていただけになったし、クリスマス前にサークル女子でリムジンを貸し切って東京タワーバックに写真を撮る予定もなんとなく風の便りで聞いている。
でもそこに自分はいなくて、これじゃ高校時代以下の生活で、一人暮らしで洗濯と掃除と料理と勉強がちょっとできるようになったくらいで、なんの華やかさも感じない。
私は一体、何をしに東京にでてきたんだっけ、と思いながらまなぽんを見た。
まなぽんはあか抜けてかわいくなっていて、昔なら選ばなかったようなファーのスヌードをまだそんなに寒くもないのに持ってきている。
「なに?」
「ううん、なんかまなぽん変わっちゃったのかなって思って」
「なにそれー、そりゃかわいくなろう、みたいな研究はしてるけど、中身は変わらないんじゃないかな」
いつも通りの笑顔で言うまなぽんに、だよね、と返しながら、やっぱり変わっていってるなぁとさみしい気持ちのまま私も笑った。
ふふふと漏れる息はキャラメルの甘い匂いがするけれど、最後にちょっと焦げたようなイメージが浮かぶ。
テーブルに置いていたスマホが、ブブブブ、と数ミリずつ動きながら光る。
見ると、メッセージの返事がきたようだった。
写真サークルいけそう? と覗き込んでくるまなぽんに、見てみる見てみる、と言いながら、綺麗な写真のアイコンをタップした。